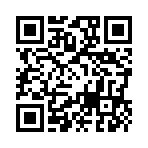2011年04月05日
蝦夷鳥兜(エゾトリカブト)

トリカブト(鳥兜・学名Aconitum)は、キンポウゲ科トリカブト属の総称で、日本には約30種自生しています。
花言葉⇒敵意、人間嫌い、美しい輝き、騎士道、復讐、後悔
誕生花⇒7月19日
草丈は30cm~1.5m程度、開花の時期は晩夏~秋(8~10月頃)です。
花の色は紫色の他、白、黄色、ピンク色など各種ありハナトリカブトと呼ばれる鑑賞用の花も存在します。多くは多年草で、沢筋などの比較的湿気の多い場所を好みます。
塊根を乾したものは漢方薬や毒として用いられ、附子(生薬名は「ぶし」、毒に使うときは「ぶす」)または烏頭(うず))と呼ばれドクゼリ、ドクウツギと並ぶ日本三大有毒植物の一つです。
美醜を表す言葉「ブス」はトリカブトの毒により歪んだ顔を表しているとの説もあります。
名前の由来は、花が古来の衣装である鳥兜・烏帽子に似ているから又は、鶏の鶏冠(とさか)に似ているからの様です。英名monkshoodは「僧侶のフード(かぶりもの)」の意味です。
北海道の先住民アイヌの人達も狩猟にトリカブト類を用いて居ました。
彼らは植物の種類ではなく、即効性や遅効性・毒の強さ等に応じて分類し調合して使っていたとの事です。
毒の強さは手の甲に笹の葉を乗せ、その上に作った毒を乗せ、笹を通して伝わって来るヒリヒリさの加減で判断していたとの事です。
羆(ヒグマ)に対する護身用に持ち歩いていたエイの毒針と異なり、即効・遅効の加減を間違えると命取りになるだけに調合や取り扱いは非常に慎重に行われました。
狩猟の際は矢の先に塗って用いられ、護身用には槍の先に塗られていました。
獲物を倒したら直ぐに矢の周りの肉は切り取られ、毒が回らない様処理されました。

虫により受粉する虫媒花ですが、下を向いたがく片の中に隠された複雑な形の花弁を持ち、学習能力の高いマルハナバチとだけ共生する「マルハナバチ媒花」の特殊な花です。
根・茎・葉は勿論、花粉・蜜にまで毒を含み蜂蜜に混入して中毒を起こした事例もあります。
毒の成分は神経毒のアコニチンで、動物の神経伝達を阻害します。
昆虫はアコニチンによって阻害される神経伝達物質を持っていない為、ハチは平気なのだそうです。
アコチニンには解毒剤が無く、半数致死量が体重1キログラム当り0.3グラムという極め付けの猛毒です。
芽出しの頃はニリンソウ・ヨモギ・モミジガサと間違い易く、誤食による事故が多い為充分な注意が必要です。
トリカブトの根は上部が肥大した逆三角形をしています。
山菜採りをして疑問を感じたら面倒でも掘って調べて見る事をお奨め致します。
百科事典で調べる⇒トリカブト、アコニチン
Posted by サヴァイバー at 19:20│Comments(0)
│適潤地の花:紫
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。